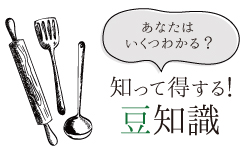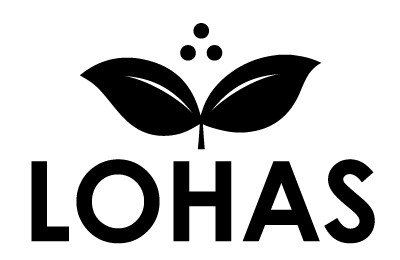ローフード通販LOHAS(ロハス) TOP > 豆知識 > 栄養と健康効果 > プロテイン > 【比較】ソイプロテインとホエイプロテイン・ガゼインの違いとは?
【比較】ソイプロテインとホエイプロテイン・ガゼインの違いとは?

ソイプロテインとホエイプロテイン、そしてガゼイン。
種類が多くて違いが分かりにくいと感じていませんか?
この記事を読めば、それぞれの原料、製造方法、吸収速度、栄養価といった特徴の違いが明確になります。
筋トレ、ダイエット、健康維持など、目的達成のためにどのプロテインを選ぶべきか、具体的な判断基準が身につきます。
最適な選択で理想の体を目指しましょう。
目次

プロテイン一覧
ロハスが販売しているプロテイン一覧はこちら。気になる方はぜひチェックしてみて下さい。
ソイプロテインの概要

ソイプロテインは、その名の通り大豆(ソイ)を原料として作られる植物性プロテインの代表的な存在です。
健康志向の高まりや多様な食生活への関心から、近年特に注目を集めています。
動物性プロテインとは異なる特徴を持ち、さまざまな目的で活用されています。
この章では、ソイプロテインがどのようなものなのか、その基本的な情報について詳しく解説します。
原料と製造方法
ソイプロテインの主原料は大豆です。
多くの場合、大豆から油分を取り除いた後の「脱脂大豆」が用いられます。
この脱脂大豆に含まれる豊富なタンパク質を抽出し、精製することでソイプロテインパウダーが作られます。
製造方法によって、主に以下の2種類に分類されます。
【分離大豆タンパク(SPI)】
脱脂大豆から炭水化物や食物繊維などをさらに取り除き、タンパク質の純度を約90%以上に高めたものです。
クセが少なく、他の食品への応用もしやすい特徴があります。
【濃縮大豆タンパク(SPC)】
脱脂大豆から水溶性の炭水化物などを取り除いたもので、タンパク質含有率は約70%程度です。
SPIに比べるとタンパク質純度は低いものの、食物繊維やミネラルなども一部残っています。
市場に出回っているソイプロテイン製品の多くは、これらのいずれか、または両方を組み合わせて作られています。
製品を選ぶ際には、どのような製法で作られているかを確認するのも一つのポイントです。
植物性タンパク質のメリットとデメリット
ソイプロテインは植物性タンパク質ならではの利点を持つ一方で、注意すべき点も存在します。 主なメリットとデメリットを理解し、ご自身の目的や体質に合っているか判断することが大切です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メリット |
【脂質含有量が低い】
動物性プロテインと比較して一般的に脂質が少なく、カロリーを抑えたい場合に適しています。 【コレステロールを含まない】 植物由来のため、コレステロールは含まれません。 【イソフラボンを含む】 大豆特有の成分であるイソフラボンを含んでいます。 【消化吸収が緩やか】 ホエイプロテインに比べてゆっくりと消化吸収されるため、満腹感が持続しやすいと言われています。 【ベジタリアン・ヴィーガンに対応】 動物性食品を避けている方でも摂取できるタンパク質源です。 |
| デメリット |
【吸収速度】
吸収が緩やかな点はメリットである一方、トレーニング直後など素早いタンパク質補給が求められる場面では、ホエイプロテインに比べて効率が劣る可能性があります。 【味や溶けやすさ】 製品によっては大豆特有の風味を感じたり、水に溶けにくい場合があります。 近年は技術改良により、味や溶けやすさが改善された製品も多く登場しています。 |
アミノ酸スコアと栄養価
タンパク質の品質を評価する指標の一つに「アミノ酸スコア」があり、食品に含まれる必須アミノ酸のバランスを示しています。
必須アミノ酸はすべて揃ってはじめてタンパク質を合成できるため、バランスが重要で、最も不足しているアミノ酸に基づいてスコアが決まります。
スコアが100に近いほど、質の高いタンパク質とされます。
ソイプロテインは、原料や製法によって違いはありますが、多くの商品はアミノ酸スコアが100になるよう調整されています。
もちろん、スコアが100でなければならないということではありません。
その場合は、他の食品との組み合わせで、不足しがちなアミノ酸を補うことで、タンパク質が合成されます。
また、ソイプロテインはタンパク質以外にも、製品によっては食物繊維やミネラル、そして前述した大豆イソフラボンなど、大豆由来の栄養素を含んでいる場合があります。
ホエイプロテインとガゼインの概要

ホエイプロテインとガゼインプロテインは、どちらも牛乳を原料とする動物性タンパク質です。 牛乳に含まれるタンパク質の約20%がホエイ、約80%がガゼインで構成されています。 同じ牛乳由来でありながら、それぞれ異なる特徴を持っています。
ホエイプロテインの特徴
ホエイプロテインは、牛乳からチーズを作る過程で固形成分(ガゼイン)と分離される液体部分、いわゆる「乳清(ホエイ)」から抽出されるタンパク質です。 ヨーグルトを静置した際に上部に溜まる透明な液体もホエイであり、私たちの食生活にも比較的身近な存在と言えるでしょう。
吸収速度と筋合成への影響
ホエイプロテインの最大の特徴は、体内への吸収速度が非常に速い点です。 摂取後、約1〜2時間で素早く消化吸収され、血中のアミノ酸濃度を急上昇させます。 トレーニングでダメージを受けた筋肉へ迅速にアミノ酸を送り届け、効率的なサポートをします。 筋力トレーニングを行う方々に人気がある理由の一つです。
味と溶けやすさ
ホエイプロテインは、一般的にクセが少なく比較的淡白な味わいで、水や牛乳などの飲み物に溶けやすいという利点があります。
そのため、様々なフレーバー(チョコレート、ストロベリー、抹茶など)の商品が開発・販売されており、飽きずに続けやすいプロテインと言えます。
プロテイン初心者の方でも飲みやすいと感じる製品が多いでしょう。
製法によってWPC(ホエイプロテインコンセントレート)やWPI(ホエイプロテインアイソレート)などの種類があり、タンパク質含有率や乳糖の量が異なります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メリット |
・吸収が速く、運動後のリカバリーや筋肉の成長に適している ・比較的水に溶けやすく、飲みやすいので初めての方にもおすすめ ・栄養価が高く、ビタミンやミネラルも含んでいる |
| デメリット |
・牛乳由来のため、乳糖不耐症の人はお腹が緩くなることがある ・吸収が速い分、腹持ちがあまり良くない |
ガゼインプロテインの特徴
ガゼインプロテインもホエイプロテインと同様に牛乳由来のタンパク質ですが、牛乳タンパク質の大部分(約80%)を占める主成分です。 チーズやヨーグルトが固まる性質は、このガゼインによるものです。
吸収速度と持続性
ガゼインプロテインの最大の特徴は、ホエイプロテインとは対照的に、体内への吸収速度がゆっくりである点です。
ガゼインは胃酸によって凝固する性質があり、消化吸収に時間がかかります。
摂取後、約7〜8時間かけて緩やかにアミノ酸を放出し続けるため、血中アミノ酸濃度を長時間安定して維持する働きがあります。
この持続性から、「タイムリリースプロテイン」とも呼ばれます。
メリットとデメリット
ガゼインプロテインのメリットとデメリットを以下にまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メリット |
・ゆっくりとした吸収による持続的なアミノ酸供給 ・就寝中など、長時間栄養補給ができない間の筋肉分解を抑制する効果が期待できる ・消化に時間がかかるため、満腹感が持続しやすい |
| デメリット |
・吸収が遅いため、トレーニング直後のような素早いアミノ酸補給が求められる場面には、ホエイプロテインほど適していない ・製品によっては、ホエイプロテインに比べて溶けにくさを感じたり、独特の風味(カゼイン臭)を感じたりする場合がある ・一般的に、ホエイプロテインよりも価格がやや高めに設定されている傾向がある |
ソイプロテインとホエイプロテインの違いを徹底比較

プロテイン選びで多くの方が悩むのが、ソイプロテインとホエイプロテインのどちらを選ぶべきかという点でしょう。
それぞれ原料や特性が異なり、目的に合わせて選ぶことが重要です。
ここでは、違いを様々な点から詳しく比較していきます。
ガゼインプロテインについても触れながら解説します。
タンパク質含有率の比較
プロテイン製品を選ぶ上で、タンパク質含有率は重要な指標の一つです。
一般的に、ホエイプロテインの方がソイプロテインよりもタンパク質含有率が高い傾向にあります。
特に、ホエイプロテインの中でもWPI(ホエイプロテインアイソレート)と呼ばれるタイプは、不純物を極力取り除いているため、90%近い、あるいはそれ以上の高いタンパク質含有率を誇ります。
一方、ソイプロテインも製品によって差はありますが、一般的には70%〜85%程度のタンパク質を含んでいます。
代表的な種類とそのタンパク質含有率の目安は以下の通りです。
| プロテインの種類 | 主な原料 | 一般的なタンパク質含有率の目安 |
|---|---|---|
| ソイプロテイン(SPI: ソイプロテインアイソレート) | 大豆 | 約80%〜85% |
| ホエイプロテイン(WPC: ホエイプロテインコンセントレート) | 牛乳(乳清) | 約70%〜80% |
| ホエイプロテイン(WPI: ホエイプロテインアイソレート) | 牛乳(乳清) | 約85%〜95% |
ただし、これらはあくまで一般的な目安であり、製品によって実際の含有量は異なります。 購入時には必ず栄養成分表示を確認しましょう。
アミノ酸スコアと栄養価の違い
タンパク質の品質を評価する指標の一つに「アミノ酸スコア」があります。
これは、食品に含まれる必須アミノ酸のバランスを示すもので、最高値は100です。
ソイプロテインもホエイプロテインも、アミノ酸スコアは100のものは多く、どちらも良質なタンパク質源であると言えます。
しかし、アミノ酸の種類ごとの含有量には違いが見られます。
特に、筋肉の合成に重要とされるBCAA(分岐鎖アミノ酸:バリン、ロイシン、イソロイシン)の含有量は、ホエイプロテインの方が豊富です。
その中でもロイシンの含有量が多い点が、筋力トレーニングを行う人にホエイプロテインが好まれる理由の一つとなっています。
一方、ソイプロテインには、大豆イソフラボンというポリフェノールの一種が含まれている点が特徴です。
イソフラボンは、女性ホルモン(エストロゲン)と似た構造を持ち、健康維持や美容面でのサポートが期待されています。
また、製品によっては食物繊維が含まれている場合もあります。
| 比較項目 | ソイプロテイン | ホエイプロテイン |
|---|---|---|
| アミノ酸スコア | 100 | 100 |
| BCAA含有量 | 標準的 | 豊富(特にロイシン) |
| 特徴的な栄養素 | 大豆イソフラボン、食物繊維(製品による) | カルシウム、乳糖(WPCの場合) |
※BCAAとは、バリン・ロイシン・イソロイシンという3つの必須アミノ酸の総称で、「分岐鎖アミノ酸」と呼ばれます。 これらは体内で合成できないため、食事から摂取する必要があり、主に筋肉のエネルギー源や筋肉の合成・修復に重要な役割を果たします
吸収速度の違いと用途
ソイプロテインとホエイプロテインの大きな違いの一つが、体内での吸収速度です。
ホエイプロテインは消化吸収が非常に速く、摂取後約1〜2時間で血中アミノ酸濃度がピークに達すると言われています。
この速やかな吸収は、トレーニングでダメージを受けた筋肉へ素早くアミノ酸を届け、効率的なリカバリーや筋合成をサポートします。
対照的に、ソイプロテインは比較的ゆっくりと消化吸収される特徴があります。
摂取後、約3〜4時間かけて穏やかに吸収されるため、血中アミノ酸濃度を長時間安定させる効果が期待できます。
この特性から、満腹感が持続しやすく、間食や就寝前のタンパク質補給に適していると言えるでしょう。
ちなみに、牛乳由来のもう一つのプロテインであるガゼインは、ソイプロテインよりもさらに吸収が遅く、約7〜8時間かけてゆっくり吸収されます。
| プロテインの種類 | 吸収速度 | 主な特徴 | 適した摂取タイミング・用途 |
|---|---|---|---|
| ホエイプロテイン | 速い(約1〜2時間) | 素早くアミノ酸を補給できる | トレーニング直後、起床直後 |
| ソイプロテイン | ややゆっくり(約3〜4時間) | 腹持ちが良い、持続的なアミノ酸補給 | 間食、就寝前、ダイエット中の栄養補給 |
| ガゼインプロテイン | 遅い(約7〜8時間) | 長時間にわたりアミノ酸を供給 | 就寝前、長時間の空腹が予想される時 |
このように、吸収速度の違いを理解し、ご自身のライフスタイルやトレーニングのタイミングに合わせて使い分けることが効果的です。
価格とコストパフォーマンスの比較
プロテインは継続して摂取することが多いため、価格やコストパフォーマンスも重要な選択基準となります。
一般的に、ソイプロテインはホエイプロテイン(特にWPC)と比較して安価な製品が多い傾向にあります。
これは、原料である大豆の価格が比較的安定していることなどが理由として挙げられます。
また、ホエイプロテインの中でも、WPC(ホエイプロテインコンセントレート)は比較的安価ですが、WPI(ホエイプロテインアイソレート)は製造工程で手間がかかるため、価格が高くなる傾向があります。
WPIはタンパク質含有率が高く、乳糖がほとんど除去されているため、乳製品でお腹がゴロゴロしやすい方にも適していますが、その分コストは上がります。
単純な製品価格だけでなく、1食あたりのタンパク質量と価格を比較して、コストパフォーマンスを判断することが賢明です。
例えば、価格が安くてもタンパク質含有率が低い製品であれば、結果的に多くの量を摂取する必要があり、割高になる可能性もあります。
| プロテインの種類 | 一般的な価格帯(1kgあたり) | コストパフォーマンス |
|---|---|---|
| ソイプロテイン | 比較的安価(例: 2,500円〜4,000円程度) | 優れている傾向 |
| ホエイプロテイン (WPC) | 標準的(例: 3,000円〜5,000円程度) | 製品による |
| ホエイプロテイン (WPI) | 比較的高価(例: 4,500円〜7,000円程度) | 価格は高いが、高純度 |
※上記価格帯はあくまで目安であり、ブランドやフレーバー、購入場所によって変動します。
ご自身の予算や、プロテインに求める品質(タンパク質含有率、付加価値など)を考慮して、最適な製品を選びましょう。
目的別のプロテイン選び方(ホエイ・ソイ・ガゼイン)

プロテインには様々な種類があり、どれを選べば良いか迷ってしまう方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、「筋力アップしたい」「ダイエットに活用したい」「アレルギーがある」といった目的別に、ホエイ、ソイ、ガゼインの中からどのプロテインが適しているのか、その選び方を詳しく解説します。
筋トレ向きプロテインの選び方
トレーニングによって筋肉を効率的に成長させたい、あるいは筋肉量を増やしてバルクアップを目指したいという方には、吸収スピードが速く、筋肉の合成をサポートするアミノ酸が豊富なホエイプロテインが最もおすすめです。
特に、筋肉のエネルギー源となり、筋肉に深く関わるBCAA(分岐鎖アミノ酸)が多く含まれている点が大きなメリットと言えるでしょう。
また、トレーニング後の30分〜1時間は「ゴールデンタイム」とも呼ばれ、体が栄養を吸収しやすい状態になっていますので、そのタイミングに飲むのがおすすめです。
ダイエット向きプロテインの選び方
ダイエット中の栄養補給や、健康的な体型維持を目指す方には、腹持ちが良く、吸収が緩やかなソイプロテインやガゼインプロテインが適しています。
これらのプロテインは消化吸収に時間がかかるため、満腹感が持続しやすく、食事の量をコントロールしたり、間食を防いだりするのに役立ちます。
ダイエット目的でプロテインを選ぶ際は、タンパク質含有率だけでなく、カロリー、糖質、脂質の量もチェックすることが大切です。
できるだけ余計な成分が少なく、低カロリーな製品を選びましょう。
1食分の食事と置き換えたり、小腹が空いたときの間食として活用したりするのがおすすめです。
アレルギーやビーガン向けプロテイン
牛乳に含まれるタンパク質や乳糖に対してアレルギーがある方や、乳糖不耐症でお腹がゴロゴロしてしまう方、あるいは動物性食品を摂取しないビーガンやベジタリアンの方には、植物由来のソイプロテインが主な選択肢となります。 ソイプロテインは大豆を原料としており、牛乳由来の成分を含まないため、安心して摂取できます。
おすすめ商品
ローフードやオーガニックフードも取り扱っている通販ショップ「LOHAS(ロハス)」では、品質と飲みやすさにこだわった美味しい大豆100%のソイプロテインを販売中です。
-
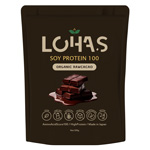
チョコレート
有機ローカカオパウダーを配合したチョコレート味。程よい甘さで初めての方でも飲みやすい味。
-

ハイチョコレート
チョコレート味にカカオを10%増量したタイプ。甘さ控えめがお好きな方におすすめ。
-
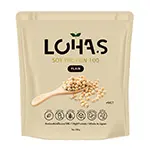
プレーン+MCT
MCTパウダーと水溶性食物繊維を配合したプレーン味。MCTパウダーはエネルギーにやりやすくアスリートやダイエッターに人気。
-

黒糖きなこ
北海道産のきな粉と黒糖を配合した黒糖きなこ。甘いのがお好きな方におすすめ。きな粉と黒糖の相性は抜群です。
-

コーヒー風味
穀物コーヒーを配合したコーヒー風味。ノンカフェインですので、寝る前の摂取や妊婦の方にもおすすめ。
「素材にこだわったソイプロテインを飲みたい」「飲みやすくて美味しいソイプロテインが欲しい」
といった方に、そのままで美味しく飲みやすい「ロハスオリジナルソイプロテイン」をおすすめします。
ロハスソイプロテインはとにかくプロテインの質・栄養価・飲みやすさにこだわっています。
原材料にもこだわり、植物性100%で、必要な物だけに絞ったシンプル設計、そして何より味が美味しいので飲みやすく、継続して飲み続けられるのが魅力のポイントです。
ソイプロテインを始めてみたいけれど、どのプロテインを選べば良いか迷っているという方、ぜひこの機会にロハスソイプロテインをお試しいただけますと嬉しいです。
お試しサイズのソイプロテイン(チョコレート味)もご用意していますので、少量から始めやすくおすすめです。
【まとめ】ソイプロテインとホエイプロテイン・ガゼインの違い
ソイプロテイン、ホエイプロテイン、ガゼインプロテインは、それぞれ原料や吸収速度が異なります。
大豆を原料とするソイプロテインは吸収が比較的穏やかで、植物性タンパク質を摂取したい方や美容に関心のある方に向いています。
一方、牛乳を原料とするホエイプロテインは吸収が速く、トレーニング後の筋肉への迅速な栄養補給に適しています。
同じく牛乳由来のガゼインプロテインはゆっくりと吸収されるため、就寝前のタンパク質補給などに活用されます。
ご自身の目的や摂取タイミング、アレルギーの有無などをふまえ、最適なプロテインを選ぶことが重要です。
監修者プロフィール

1968年生まれ。
JFAA公認フードアナリスト、調理師米国LLCAI公認ローフードシェフ&インストラクター。
外資系大手食品会社を経て、 2007年、札幌に北海道初となるローフード専門店「ローフードカフェLOHAS」をオープンする。
ローフードシェフの学校である米国Living Light Culinary Arts Instituteで学び、 同校公認のローフードシェフ&インストラクター資格を取得。
全国各地で講演活動や料理教室を行い、ローフードの普及に努めている。
・ 土門大幸著書一覧
・ 2019 VEGETARIAN AWARD 書籍賞受賞
・ 一般社団法人 日本ローフード協会 理事長
SHOP NEWS







 オーガニックドライマンゴー
オーガニックドライマンゴー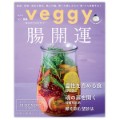 veggy
veggy 有機メープルシロップ
有機メープルシロップ 有機ローチアシード
有機ローチアシード オーガニックパンプキンシード
オーガニックパンプキンシード イタリア産
イタリア産 生カシューナッツ
生カシューナッツ 生ミックスナッツ
生ミックスナッツ デグレットデーツ
デグレットデーツ ドライ白いちじく
ドライ白いちじく オートミール
オートミール ローカカオバター
ローカカオバター ローカカオパウダー
ローカカオパウダー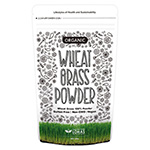 有機ウィートグラス
有機ウィートグラス ローアガベシロップ
ローアガベシロップ 生アーモンド
生アーモンド 生カシューナッツ
生カシューナッツ 生くるみ
生くるみ 生ピーカンナッツ
生ピーカンナッツ 生マカダミアナッツ
生マカダミアナッツ 生ピスタチオ
生ピスタチオ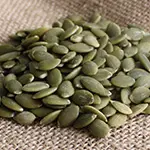 パンプキンシード
パンプキンシード ひまわりの種
ひまわりの種 無添加8種トレイルミックス
無添加8種トレイルミックス ありがとうナッツ
ありがとうナッツ ドライいちじく
ドライいちじく ゴジベリー(クコの実)
ゴジベリー(クコの実) はみなつめ
はみなつめ レーズン
レーズン デーツ
デーツ 4種類の
4種類の プルーン
プルーン ドライフルーツミックス
ドライフルーツミックス ありがとう
ありがとう ローカカオニブ
ローカカオニブ ロハスオリジナル
ロハスオリジナル ロハスオリジナル
ロハスオリジナル ブロッコリーの種
ブロッコリーの種 ローゴジベリータルト
ローゴジベリータルト ローチョコレート
ローチョコレート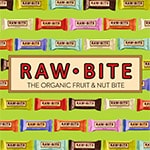 RAWBITE
RAWBITE ラカンカ
ラカンカ ロハステビアスイート
ロハステビアスイート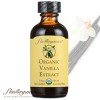 Flavorganics
Flavorganics ドライフードエアー
ドライフードエアー プレミアムNEW
プレミアムNEW スチームオーブン
スチームオーブン ミキサー
ミキサー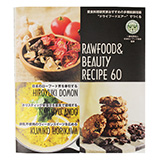 RECIPE60
RECIPE60 ローフードレシピ
ローフードレシピ ローチョコレートVIVO
ローチョコレートVIVO 木の実ロータルト
木の実ロータルト チョコレートロータルト
チョコレートロータルト 導入美容液リムゲン
導入美容液リムゲン ロハスオリジナル
ロハスオリジナル ファスティングダイアリー
ファスティングダイアリー 難消化性デキストリン
難消化性デキストリン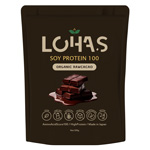 ロハスオリジナル
ロハスオリジナル プロテインシェイカー
プロテインシェイカー 北海道産
北海道産 北海道産
北海道産 北海道日高産
北海道日高産 特別栽培米
特別栽培米 ハーバルコーヒー
ハーバルコーヒー SCS
SCS